2026年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2026年2月23日(月)
2026年2月22日(日)
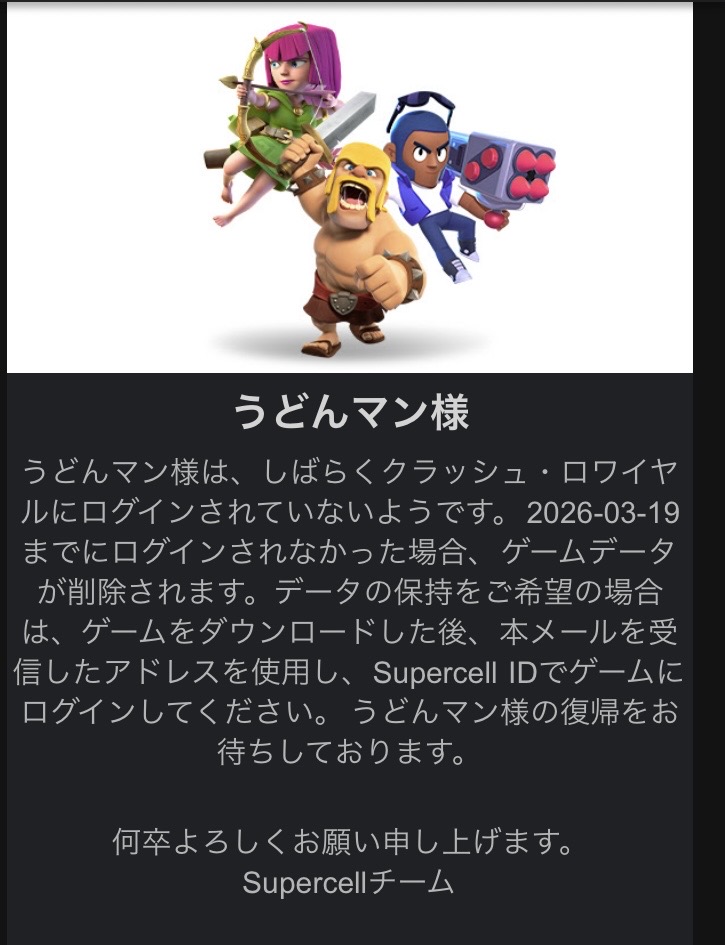
大昔にハマっていた「クラッシュ・ロワイヤル」のデータが消えそうなのだ。
これはいけない、と慌ててログインしたら、あれよあれよという間に再燃。
この戦略性がおもしろいんだよなぁ。
いわゆる日本のソシャゲ的な「ひたすら時間をかけてレベル上げしないと追いつけない」「課金すればするほど強くなる」「イベント限定キャラのために時間が溶ける」のような要素はなく、きっちり思考して実力を積み上げなければ勝てない仕組みが気持ちいい。
考えてやれば、初心者でもしっかり勝てるし、気軽にやる分には課金の必要もない。
やっぱり、努力が実る健全なゲームがやりたいよなぁと考えるのであった。
一プレイが非常に短いので、スキマ時間でできるのも好きだったり。
スマホでできるゲームの形として、完璧すぎると思っている。
#ゲーム
2026年2月21日(土)
泡坂妻夫「しあわせの書―迷探偵ヨギガンジーの心霊術」。
以下、ふわっとしたネタバレありの感想。
最近ヒットした、とある本の元ネタとなったらしい本なのだが、その本と同じく、「おもしろい!」と言うよりは「手が込んでるなあ……」という一冊。
ミステリ界の奇書であり、一読の価値はあるのだけれど、この手の本は種を知ってしまったらもう読み返すことはないなあ、という点でやや物足りない気持ちもある。
奇術師としても知られる泡坂妻夫ならではの奇想天外なトリックで、これを思いついたとしても、実現させるのは相当大変だろうなと思う。
メイントリック以外の部分も意外と読ませてきたり(サブトリックもよく考えるとやや変化球で異様である)、当時の新興宗教団体の絶妙な怪しさ、主人公がヨーガの使い手、とヘンテコの詰め合わせみたいな一冊。
この変な感じが旅行の特別な気分に合っていたと思う。
なお、「これって、Kindle版はあるんだろうか……?」と気になって、読み終わってからすぐにAmazonのサイトに飛んだのはたぶん自分だけではないだろうな。案の定、Kindle版はなかった。
泡坂妻夫作品、ぼちぼち読み進めたいなあ。畳む
#読書
2026年2月20日(金)
昨年、楽しかった群馬をまた行き先としてチョイス。
一日目のメインは、桐生にあるミールス屋に行くこと。
特に電話などをしないで向かってしまい、「もしかして、やってないのでは!?」とヒヤヒヤしたが、ちゃんと営業していた。
無事においしいミールスにありつけた。
桐生を歩いて散策して、the・地元の本屋!という感じの書店で文庫本を買った。
帰りの電車が一時間に一本しかなかったので、余った時間は桐生市立図書館へ行って、漫画を読んでいた。
本数の少ない電車ばかり乗り継いだため、ほとんどの時間を電車と電車待ちで過ごす旅になった。電車大好きなので、かなりいい感じ。
明日はなにをするか、まだ何も決めていない。
#旅行
2026年2月19日(木)
2026年2月18日(水)
まず、入り口で名前と連絡先を書き、入館用パスをもらう。
食券を買って、料理を受け取って席へ。
素朴な素材の味を生かした定食で、小鉢は好きなものを自分で取って選べる。
最後はトレイに食べ終わった器を乗せたままベルトコンベアに乗せると、そのまま洗い場へ流れていく。
大学の食堂にタイムスリップしてきたみたいで、わくわくしたなあ。そういえば食堂ってこんなんだった。
ちょうど埼玉フェアだったので、埼玉の食材を使った料理が楽しめた。
また行きたいな。
#イベント
2026年2月17日(火)
最初はグラフィック面にややがっかりしていたが、7と8と維新のハイブリッドのようなミニゲームが嬉しくて、もりもりやっている。
ここへきて、維新の菜園や料理が戻ってくるとは。
一番好きなのが維新無印なので、維新要素が多いと嬉しくなるのであった。
#ゲーム
2026年2月16日(月)
ブローティガンは初読だったのだが、すごく好きな雰囲気で、一気に読み終わってしまった。
ほとんどのものが『西瓜糖』でできている世界。
そして、そこにあるコミューンのような場所・アイデス(iDeath)。
そこでは、淡い感情を持った人たちが、透明で静かな日常を送っている。
かつてはわたしたちと同じように言葉を話す虎たちが住んでいて、人々は虎たちに食い殺されていった。今はもう、虎たちはいない。
アイデスでなにが起こるのかを、『わたし』は西瓜糖の言葉で語っていく。
世界は不気味なほどに淡々としていて、死も暴力も、薄まったような感情によって処理される。
悲しくないわけではないだろうが、(iDeathという名前が指し示すように)死と隣りあう自分を常に意識している彼らは、誰かが死んでも、あまり動揺しない。きっと、予測の範囲内なのだろう。
現実とは似ても似つかないようでいて、彼らの日常はわたしたち読者の日常によく似てもいる。
不思議な国に迷い込んだような、独特な読後感だった。
訳者の方のセンスの要素もかなり大きいのだろうと思うが、読みやすく、染み入るような文体が好きだった。
ブローティガンの他の作品も読みたいな。畳む
#読書
2026年2月15日(日)
M-1グランプリに突然出ることになる。しかも決勝。
有名な芸人の相方としての出演なのに、ネタについては何も知らないまま本番に突入しようとしている。漫才自体も一回もやったことない。絶体絶命の状況。
絶体絶命なのに、なぜか「でも、本番になったらなんとかなる気がする~」とちょっとだけ楽観している。
そして本番に突入する前に目が覚める。
そんな夢。
M-1の熱がまだ冷めていないのだろうか。
最近はお笑いについてはややクールダウン中なのだが(集中力がすり減っているため)、M-1のことはやっぱりちょこちょこ思い出す。
もうすぐR-1があるから、そっちはちゃんと見たいな。
昨年、録画しそびれて見られなかったんだよな~。
#夢日記
2026年2月14日(土)
前はなんとなく億劫になってやめてしまったのに。
やっぱりゲームには巡り合わせがある。
人生において、このゲームが今は必要!と思う時期があるのだ。
そんな気がする。
#ゲーム
2026年2月13日(金)
ようやく酒場ランクが10に。そして、一日の売上げ10万超えのトロフィーもゲット。
しかし、物語は終わらない。もうちょっとだけ続くんじゃ。
ラストダンジョン(だといいな、違うかも)の敵が強い、強すぎる。
適正レベルで挑んでも死にまくるので、レベル上げが必要だろうな~。
トロコンまでの道のりはまだまだ遠い。
何も考えたくない、疲れた日に最適のゲームだ。
#ゲーム
2026年2月12日(木)
個人的には「ゲームを始めた日」(第一章クリア、冒険の旅に出た、初めて戦闘をしたなど)にもらえるトロフィーがあると、記録としては助かるなあと思うなどしていた。
難易度の高い項目をクリアしたときにのみトロフィーを渡すべきだと思っていそうな開発者も多くて、それはそれで理解できるんだけど、長期間プレイすることになると「いつ始めたのか」が一目でわかるのがいいなと思ってしまう。
やたらめったら配りまくるのも品がないけど、物語の節目にはトロフィーがあったほうが、あとから見返せるからいいんだよなー。
#ゲーム
2026年2月11日(水)
2026年2月10日(火)
ここ最近のユヤタン作品のなかでは、一番かつてのユヤタンっぽいお話かもしれない。
かなりマイルドではあるが、イヤ~な性欲の描写、女性の内面掘り下げの薄さ、イヤミスかつ馬鹿げた世界な結末と、鏡家サーガ的な要素が多くてよかったと思う。
なお、価値観のアップデートはまったくないので、「令和にこの感じはきついな……」という部分もある。このテンションを手放しで楽しめなくなった自分が大人になったということなのか。変わらないユヤタンでいてくれることを喜ぶべきなのか。複雑な心境。
むしろ逆に、もっと倫理観を壊してアクセルを踏み込んでもよかったのではないかな~、と思ったりもした。ここで変にブレーキを踏んでしまうと、ユヤタンの強みがなくなってしまうので。
ともあれ、令和になってもユヤタンはユヤタンだったということを証明する一冊だった。レビューサイトなどを見ていると、この本で初めてユヤタンを読んだという人がたくさんいて、むしろ古参ファンのほうが少なかったりしていて、時代の移り変わりを感じた。
あのころファンだった人たちは、今どこで何をしているんだろう。畳む
#読書
2026年2月9日(月)

酒場ランクが8になり、稼ぎが加速してきた。気持ちいい。
余った料理を全員に食べさせて、レベルも稼いでいく。
いい感じに進んできたなあ。ここからが終盤戦だろうか。
#ゲーム
2026年2月8日(日)
当時、8巻まで読んで、途中でやめてしまっていた。
約10年ぶりに最初から読み直してみて、やっぱり8巻あたりで一度減速した感じはあったのだが、そのあとはちゃんと盛り返していて、おもしろかったなあ。粗削りでパワーのある漫画。
人間の心が視覚として「見えて」しまう超能力を持つ少年が、吹奏楽部でみんなの心を救済しながら、指揮者として成長していく様子を描く、音楽部活漫画。
超能力の描写がかなり行きすぎ・やりすぎの感があり、最終局面では外見上は音楽漫画というよりも異能バトル漫画のような様相を呈してくるのだが、そこが漫画として唯一無二で、存在感がありまくる。
こちらの心をグイグイ掴んでくる優しい漫画で、また最初から読み直したくなるのだった。
また、部活漫画のキャラとは思えない突き抜けた邪悪な敵キャラ・黒条の描写も凄まじい。
もし、部活漫画のキャラの邪悪さを競う選手権があったら、こいつを超えるやつはいないのではないかと思う。
確実に、この能力を使って何人か殺してるのでは??という風格がある。さすがに邪悪すぎる。
「いやいや、嘘じゃん」と思ってしまう部分もあるのだが、その嘘をうまく活用して魅せてくるのがテクニカルで楽しい。
実際の吹奏楽部の人たちはこれを読んでどう感じるのだろうか。気になる。畳む
#読書
2026年2月7日(土)
お休みの日に、狙いを定めて電車で食べに行く。
必ずチャイをつける、という自分ルールがある。
ついでにお店の周りを散歩して、知らない街を堪能する。
次はどこへ行こうか、楽しみだ。
2026年2月6日(金)
単純作業だけやりたいときに本当に効く。
もうすぐ、龍が如く3極が来るぞー!と騒いでいたら、突然パラノマサイトの続編が発表された。もうすぐ発売。
ドラクエ7も気になっているのに……新作が渋滞しそうだ。
なんなんだ、2月。新作だらけすぎるぜ。
#ゲーム
2026年2月5日(木)
「ふてほど」なニュースに「もうええでしょう」する平和なイベント。
これまで取り扱ったニュースのまとめ、社内の防犯カメラを使いながらの衝撃的なニュース報告など、充実した内容でよかった。ずっと見られるようにしておいてほしいくらい。
傘泥棒に何度も遭遇する鬼谷さんが楽しすぎたなあ。
唯一、残念だったのは、配信プラットフォームの問題だと思うんだけど、10分再生すると止まってしまうこと。そして再読込すると、進行状況がリセットされ、動画の一番最初に戻るということ……。
コメント欄でもたくさん被害者がいたんだけど、どうにかならないのかなあ。
もう一度見返したいのに、10分刻みのリセットはさすがにしんどすぎて断念してしまった。畳む
#イベント
2026年2月4日(水)
2024年の本屋大賞受賞作「成瀬は天下を取りにいく」の続編。
続編でありながら、前作と遜色のないおもしろさなのが凄まじい。個人的にはこちらのほうがおもしろかったかもしれないくらい。
以下、軽いネタバレありの感想。
「成瀬は天下を取りにいく」は親友・島崎みゆきとの友情譚でもあったのだが、今回は進路が分かれてしまったため、島崎の話は少なめ。しかし、ちゃんと存在感はある。
話の途中で、受験があり、大学生活がはじまるのだが、そのはじまりの部分はさらりと流していて、イベントとしては扱っていないのも新しいなと思った。
成瀬シリーズが王道な青春ストーリーでありながらどこか斬新に感じられるのは、他の青春ものでは大々的なイベントとして扱われるものを、そういうふうには扱わないという部分の印象が大きいのかもしれない。扱うときもあるけど。
あと、マイペースに発信を続けている弱小YouTuberを前向きな存在として描いているのも今風で好きだったりする。
物語的なテンプレとして、YouTuberってマイナスのイメージを持った存在として描かれがちだと思うんだけど(入っちゃいけない場所に入る、金やバズのためならなんでもやる、私刑を行うなど)、実際にはYouTubeで継続的に発信できる人って、売れる・売れないにかかわらず、すごく努力している人が多い。ネタを探して、撮影して、発信しつづけるというのは、ふつうの人にはできないことだと思う。
みんながみんな悪いことをしているわけではないのに、「そういうものだから」という偏見でクズに描かれがちな状況になんとなくモヤモヤしていたので、今回、成瀬が怪しげなYouTuberとふつうに友だちになっている描写、好きだったなあ。
ラストでは、これまでの話に出てきた人物たちが集合して成瀬を探すという展開が熱かった。
成瀬の行き先が判明したときは「こんな場所にいたとは……! たしかにこれしかない!」と納得の嵐だったなあ。
3巻で終わってしまうとのことなんだけど、まだまだ続いてほしいなあ。畳む
#読書
2026年2月3日(火)
今年はサーモンたっぷりの恵方巻。うまい。
特に恵方とかは考えず、ただただおいしいから買ってきている。
ちなみに、昼食にはセブンイレブンの小さい恵方巻っぽい感じのやつと、イワシのつみれ汁を食べた。
つみれ汁がめちゃくちゃおいしくて、また食べたくなった。
これだけ恵方巻とイワシを食べまくったので、節分は完璧にこなせたといえるだろう。
#買い物
2026年2月2日(月)
第1話・第2話であった、合六さんのおいしい料理のコーナーがなくて寂しかった。
が、そのかわりに、ガストで儀堂と一香がミルクレープを食べるシーンがあった。
緊張した会話のあとの、息抜きのミルクレープ。おいしそうだ。
合六さんの料理は命をかけなければ食べられないが、ガストのミルクレープならわれわれも食べられるのではないか。
そう思って、朝からガストのメニューをチェック。
……ない。ミルクレープがどこにもない。
どうやら、ドラマの中だけの架空のメニューだったようだ。
がっつり「ガスト」って書いてあるのに、ないの!?という驚き。
本物のガストのスイーツでは、儀堂(早瀬)の舌を満足させられないという判断だったのだろうか……。
どうしてもミルクレープが諦めきれなくて、ふと入ったはま寿司でデザートにミルクレープを食べてしまった。おいしかった。
ガストは、今からでも期間限定で儀堂と一香のミルクレープを販売してくれたら、みんな食べるのではないか……と思ってしまった。
#ドラマ
2026年2月1日(日)
ハラハラ・ドキドキで、引っ張られている謎もいくつもあって、わくわくする。
ちなみに、推しは合六さん。ちゃんと最後まで生き残れるかなあ……。
そういえば、日曜劇場を完走したことってあるんだろうか?と思い、過去作品の一覧を見てみた。
VIVANT……ノリが合わなくて途中でやめた。
海に眠るダイヤモンド……そのうち見ようと思って録画を残してあるけど、まだ二回くらいしか見られていない。
ノーサイド・ゲーム……これもあんまり合わなくてやめちゃった。
陸王……再放送でチラ見したかも。
JIN-仁-……これも再放送で何回か見た。
という感じで、直近のものはフルでは見ていなかった。
半沢直樹も見たことないし、縁がない枠なのだなあ……。
もしかして、一回も完走できていないのでは……?という不安を残しながら遡っていくと、「空飛ぶ広報室」と「GOOD LUCK!!」があった。
よし、ちゃんと見ているやつあるぞ!!
ラインナップだけ見ると、飛行機が好きすぎる人みたいだ。
「空飛ぶ広報室」は野木亜紀子作品だからという理由で後から見たんだけど、このあとで「ファントム無頼」や「エースコンバット7」にハマることを考えると、航空自衛隊の話だから好き、という要素もあるのかもしれない。ファントム無頼を踏まえたうえで、また見たいなあ。
あと、昔すぎて自信がないのだが、「パパとムスメの7日間」も全部見たような気がする。たぶん。
1990年代まで遡ってみたが、この3本しか完走したものが見当たらないという。
ドラマを見ていない人生だなー。
そんな人が追いかける「リブート」。今回は完走なるか。
#ドラマ
2026年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2026年1月31日(土)
おいしいのでまた買いたいなあと思っていたが、近所のスーパーに紅まどんなの姿はもうなかった。毎回チェックしているのに、影も形もない。
人気すぎるのか、時期が限定されているのか。それともスーパーに行く時間が悪いのか。
幻の紅まどんなとは、もうお別れなのかもしれない。早いな。
#買い物
2026年1月30日(金)
オモコロウォッチは全部聞いてしまったので、聞いていない匿名ラジオの回をちょっとずつ聞いている。龍が如くをしながら。
お蔵入りになった217回の思い出を語る218回がおもしろかった。
違法アップロードという体裁で、217回のパチモノがYouTubeの別チャンネルでアップされているという芸が細かくて好き。神回だった。
#ラジオ
2026年1月29日(木)
闘技場関連のトロフィーが多いのだが、仲間集めと仲間のレベル上げがかなりの虚無。
お金でもレベル上げできるけど、お金を稼ぐためにまず闘技場を回さないといけないので、そうなるとふつうにレベル上げしてもいいのでは……と悩む。
めんどくさそうでノータッチなのはキャバクラ。まだひとりしかクリアしてない。
あと、ビリヤードのピタゴラチャレンジがなかなか難しい。これは練習しないと無理かも。
プレイスポットで遊ぶだけでもらえる系を獲得しつつ、合間合間にレベル上げ。
そんな感じでちょっとずつ埋めていっている。
#ゲーム
2026年1月28日(水)
「龍が如く7外伝 名を消した男」をクリアした。
寄り道含めて17時間くらい。
久しぶりに龍が如くの世界をエンジョイできてよかった。
「7の外伝」の要素もあるんだけど、どちらかというと「6の後日談」のイメージが強い話かもしれない。意外と、7の話は控えめかも。「8の前日談」部分もすこしあった。7と8をやり直したくなるなあ。
8で『桐生一馬の終活』をはじめたのがかなり斬新だったのだが、7外伝を見ると、終活に至るまでの心境が細かく描かれていておもしろかった。
坐禅を組んでマインドフルネスして、これまでの人生を整理しつつ、終活をはじめるゲーム主人公。今までにこんな存在がいただろうか……?
シリーズ主人公を丁寧に世代交代させつつ、前主人公の人生をきれいに畳んでいく、という作業が見ていて気持ちいいんだよなあ。
終活にあたり、これまでの龍が如くに出てくる要素をもう一度出し直して精算していく(獅子堂、三代目西谷誉あたりのくだり)という部分が好きだった。ジングォン派が好きだから、今回も出てきて嬉しかったなー。
ビジュアルやアクション的にはやや雑な部分もあるのだが、シナリオがいいので帳消しになっている気がする。
このあとはトロフィー回収をやろうと思っている。
マラソンが進んで、ナンバリング本編未プレイなのが4と5と8外伝、プレイしたけど未クリアなのが3という状態になっている。
次は4か5をやろうかと思っていたけれど、極が順調に出るとしたら、4と5も極発売を待ってからやったほうがいいのかもしれない……というジレンマ。
とりあえず、極3と3外伝をやって、そのあとは8外伝かLOST JUDGMENTかなー。畳む
#ゲーム
2026年1月27日(火)
気になって探してみるのだが、行動範囲の店には見当たらない。
悪夢が見たいわけではないんだけど、どうしても気になって、チーズ売り場をさまよっている。
#買い物
2026年1月26日(月)
ヘルパゴスリターンズ、めちゃくちゃおもしろかった。
以前のヘルパゴスも相当神回だったのに、人数を増やして、さらに上を行くというミラクル。
みくのしんさんが光の主人公すぎて大好き。実在する人がこんなに主人公なことあるか?
乱発するのもよくないんだろうけど、またやってほしい。何度でも楽しめそう。
#視聴メモ
2026年1月25日(日)
2008年から継続して記録しつづけて、ついに6000。頑張っているぞ。
読書メーターというサービスそのものが長くつづいてくれていることも嬉しい。
いつまでも読書家と並走する存在であってほしいなあ。
#読書
第174回直木賞受賞作。
実は直木賞ってそんなに読んできていなくて、途中で読むのをやめたりした作品が多いのだけれど、これはサクサク読めて好きだった。
大正から戦後までのカフェーの風景を、女給の目線から描くお話。
フェミニズム的な感じや、戦争の恐ろしさみたいなパートもすこしだけありつつ、基本は女性たちの生活をのどかに描写している場面が多くて読みやすいと思う。いい雰囲気のカフェーだなあ。
大河的なテンションも好き。
映画化、ドラマ化したら映えそうだなと思った。
人物が多いから、ドラマのほうがいいかな。畳む
#読書